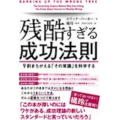第2図書館係補佐 又吉直樹著
本の紹介をするというのは、難しいものです。
わたしは本の感想をブログに書いたり、この記事のようにブックレビューを書かせてもらったり、読書会で最近読んだ本を紹介したりしているので、本を紹介するという作業には慣れているはずです。
ですが、「本を紹介するのが上手くなった」と実感したことは今のところありません。
百歩譲って、「書くこと、話すことは上手くなった(ような気がする)」と感じることはあっても、「いや〜、今日は完璧に伝えられたわ〜」なんて思うことは、まずありません。
というか、著者の人が時間をかけて魂を込めて書いた本を、わたしなんかが良かったとかそうじゃなかったとか判定するのは、そもそも大変おこがましい行為なのです。
それを認識した上で「本について書くことや紹介することは、自分のためになるはず(そして上手く行けば、読んだ誰かのためにもなるはず)」と思って、腹をくくって書いてみるわけです。もちろん、何回も見直します。
でもまあ、何度直したとしても、出来上がった目の前にある文章を自分で読むたびに「本当にこれでいいのだろうか」と不安な気持ちになります。
本の内容はこう理解したけどこれで良かったのだろうかと、自分の理解力に自信が持てないこともあるし、この書き方で本の良さが伝わっているのだろうかと、自分の表現力の至らなさに不安になることもあります。
読めば読むほど疑心暗鬼になるのですが、最後は「今のわたしに書けるものはこんなものだ」と諦めて、自分なりのレベルでなんとか仕上げに持っていくしかありません。
本書は、著者の又吉直樹さんが「本の紹介をしている本」です。
しかし、よくある本のレビューや感想文とは異なる角度で本を紹介しています。まず、紹介する本の内容については、文章の最後にほんの少ししか触れられていません。そして「おもしろかった」など、本に対して直接的な評価をするものでもありません。
では何が書かれているのかと言うと、その本のストーリーに関連した、又吉さんの個人的な思い出話です。
「僕の人生にこういうことが起こりました。この本にはそういうことが書かれています。」そんな風に語られています。
1つの話は文庫本で数ページほど、そのうち、個人的な思い出、つまりエッセイ部分が9割で、末尾でちょこっとだけ紹介する本の話に触れます。
テレビで見る又吉さんが目の前で語ってくれているような、テンション低めだけどなんだかくすっと笑ってしまう、でも胸をぎゅっと掴まれるエッセイ。そして最後にふと1冊の本が現れる。
“僕の役割は本の解説や批評ではありません。(中略)僕は自分の生活の傍らに常に本という存在があることを書こうと思いました。” (2011年 幻冬舎よしもと文庫 又吉直樹「第2図書係補佐」5ページ)
これが「本を真に愛する人が考えた、本を人に伝える方法」なのかと、目が鱗が落ちたような気持ちになった一冊でした。
Written by げんだちょふ(ロシア)